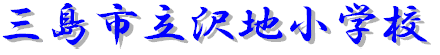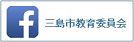つきましては、ブログのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている場合には、大変お手数をおかけいたしますが、変更後の新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いいたします。
今後も、引き続きご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■変更時期
2023年1月30日より
■変更前: 旧ブログ(http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m110/)
■変更後: 新ブログ(https://schit.net/mishima/sawaji-e/)
メッセージ欄
2015年12月の日記
▼ 2015/12/09(水) 「くらりか」による<理科教室ふしぎ不思議> 1



「皆さんは、おとなになったら、何になりたいですか?」
―そんな投げ掛けで、授業がスタートしました。
今日は、「くらりか」の方々を講師にお招きし、5年生の2クラスを対象にした<理科教室>が開かれました。(各クラス・2時間ずつ)
この方々は、“理科嫌い”の子どもを無くしていくことを目的として、各地で活躍されています。本校でも、今年度はもう2回も、科学クラブがお世話になりました。
“理科好き”の子は、将来、「科学者・博士・研究者・医者・看護師・薬剤師・エンジニア・設計士・発明家」になれる可能性がある……そんな夢を語りながら、子どもたちの心をくすぐっていきます。
そして、「理科マジック」が子どもたちの前で繰り広げられました。“振動”や“磁力”や”圧力”を活かした、<理科>を意識させるマジックが展開されます。これで、子どもたちの目をぐいっと引きつけ、心をぎゅっとつかみました。
さらに、今日の活動に結びつく、中学や高校で学ぶ『フレミングの左手の法則』を挙げ、“電流”・“磁界”・“そこに生じる動き”の関係まで、子どもたちに熱く語られました。
▼ 2015/12/09(水) 持久走記録会 3



「中学年の部」は、「3年女子→3年男子→4年女子→4年男子」の順にスタートしました。4レース共、“1.5㎞”のコースを走ります。
1・2年生の後だからでしょう、やはり、たくましさを感じます。子どもたちが成長していく過程が見られるような気がしました。
昼休みも真っ先に運動場に飛び出して来るような、3・4年生たちの走る姿からは、疲れを知らないやんちゃっぷりが感じられました。
きっと、動くことが楽しくてしかたない年頃なのでしょうね。これからも、毎日毎日精一杯体を動かして、生き生きと生活していって欲しいものです。
多くの学校の<持久走記録会>が、「運動場や敷地内をひたすら何周か走る」という形に変わってきています。そんな中、本校のように、敷地から飛び出して校区の道路を走れるのは、幸せなことだと思います。子どもたちは、移り変わる景色の中から、目的地を目据えて走って行くことができるのですから……。
しかし、ここには、沿道の各所に立って、子どもたちの安全を確保してくださるPTAの学年部員の方々の存在が欠かせません。この日も寒い中で教育活動を陰から支えてくださったことに、心より感謝申し上げます。おかげで、全ての学年の子どもたちが、無事に元気に完走できました。
そんな子どもたちにも、もちろん大きな拍手を送りたいと思います。こうして、また一つハードルを跳び越えた子どもたち。―さあ、次の目標は何でしょうか。再び力強く歩み出しましょうね!
▼ 2015/12/09(水) 持久走記録会 2
「低学年の部」は、「1年女子→1年男子→2年男子→2年女子」の順にスタートしました。この4レースは全て、“1㎞”のコースを走ります。
1年生は、小学校で初めての<持久走記録会>です。
4月に小学校に入学した頃は、あんなに小っちゃくて頼りなげだった子たちが、こうして“1㎞”の道のりを走り抜いていく姿には、感動すら覚えます。……応援にいらした親御さんたちも、きっと我が子の成長ぶりを心からうれしく思ったことでしょう。お祖父ちゃん・お祖母ちゃんの姿も多く見られました。お孫さんのがんばる姿を夢中で見守る姿に、大きな愛情が感じられました。
2年生は、1年生の一生懸命な姿に触発されたのでしょう、男女とも全速力で走り出しました。まるで、“短距離走”のようなスタートだったので後半が心配されましたが、みんな見事に走り抜きました。沿道や運動場のあちこちからかけられる親御さんたちの声援は、子どもたちの心をこんなに高めるのですね。
「低学年」の子どもたちは特に、親御さんに、自分のよりよい姿をほめて欲しいという気持ちが強いのでしょう。みんな、本当によくがんばりました。


▼ 2015/12/08(火) 持久走記録会 1



今日の午前中、高学年・低学年・中学年の順に、「持久走記録会」が開かれました。
4月から毎朝、この日に向けて走り込んできた子どもたちが、いよいよ成果を発揮する日です。今日は幸いなことに、それほど気温も低くなく、風もほとんど無い、穏やかな「持久走日和(ひより)」でした。
高学年は、「5年生女子→5年生男子→6年生女子→6年生男子」の順番で、レースが行われました。4レース共、運動場から東門を飛び出し、沢地川沿いを走る“2㎞”のコースです。
4年生の時より“500m”も距離が伸びた5年生でしたが、沿道や運動場で応援するたくさんの親御さんの声に励まされて、男子も女子もみんなしっかり走り抜くことができました。
6年生は、“小学校最後”の挑戦となります。どの子からも、最高の自分を見せようという意気込みが感じられ、<最高学年>らしい力強さで駆け抜けていきました。そして、親御さんたちの声援からも、“小学校最後”の我が子の勇姿を目に焼き付けておこうというような温かい愛情が感じられました。
▼ 2015/12/04(金) わくわくサンシャインアートで楽しもう 15



「一等賞」は、3班に決定しました。低学年の子どもたちが思わず飛び上がりました。一人ひとりの首には、まぶしく輝く金メダルが、「うるま」さん・「でるび」さんの手からかけられました。(また、学校には、「うるまでるび」作の絵本もいただきました。)
……どの班のどの作品も、甲乙付けがたいものだったと思います。
また、作品を完成させるまでの過程を知っているからこそ、子どもたちの苦労やがんばりを目の当たりにしているからこそ、本当は、どの班にも「一等賞」をあげたかったのですが……。
ここに、「うるま」さんの、<作品は必ず評価されるという現実を知らせる>というねらいがあったのです。―そうですね。“社会”の仕組みを実感させる上で、大切なことなのでしょうね。
「うるまでるび」さんとの、夢のような3日間が終わりました。初めての様々な体験がぎっしり詰まっていた3日間でしたが、あっという間に過ぎ去った3日間でもありました。
このワークショップの企画・準備・運営に携わってくださった、「うるまでるび」さん、そして、「沢地小学校支援地域本部」・「粋なおやじの会」・「三島市教育委員会文化振興課」「日大国際関係学部・神山ゼミ」の皆さん、本当にありがとうございました。
また、本日“審査員”としてご来校くださった「保護者の皆さん」、「地域の方々」、「沢地幼稚園の皆さん」にも感謝申し上げます。
そして、体育館の床を敷き詰めた大量の紙を提供してくださった「特殊東海製紙株式会社」さん、アニメーション作りに使うパソコンソフト・「PICMO」に関わってくださった「株式会社スワベ商会」さんにも、陰で力強く支えられました。
たくさんのいろいろな方々のおかげで、<わくわくサンシャインアート>をやり遂げられたこと……沢地小の子どもたちは、本当に幸せ者ですよね。
最後の最後に、「うるまでるび」さんから子どもたちに、素敵なアニメーションのプレゼントがありました。『東日本大震災』で被災した子どもたちの心を励ますために作られた、温かい素敵な作品でした。
美しいアニメと共に、坂本龍一&デイヴィッド・バーンの『サイケデリック・ アフタヌーン』という曲が、体育館に心地よく流れていきます。……充実した3日間が、静かに静かに幕を閉じていきました。