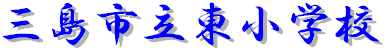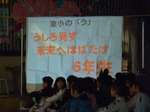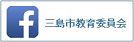つきましては、ブログのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている場合には、大変お手数をおかけいたしますが、変更後の新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いいたします。
今後も、引き続きご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■変更時期
2023年1月30日より
■変更前: 旧ブログ(http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m101/)
■変更後: 新ブログ(https://schit.net/mishima/higashi-e/)
メッセージ欄
2013年3月の日記
▼ 2013/03/06(水) 幼稚園児による「給食」参観



昨日(5日)は、この4月から“本校の1年生”になる、お隣の東幼稚園児(年長組)が、現1年生の「給食」の様子を参観にやって来ました。
1年生の子どもたちは、幼稚園からのかわいらしいお客さんに、かっこいい“お兄さん・お姉さん”ぶりを見せつけてやろうと、張り切っていました。
給食当番の子たちは自分の役割をてきぱきとこなし、ほかの子たちも黙って列を作り、スムーズに流れていきます。そんな、1年生の、落ち着いた、きびきびした態度に、園児たちも感心していた様子です。
「いただきます」の後も、やはり、いつもとはちょっと違っていました。子どもたちが食べ物に「はし」をつける前に、この日も先生が、
「苦手な物を減らして欲しい人はいらっしゃい。」と声をかけました。
しかし、いつもとは違って、減らしてもらいに来る子がほとんどいないのです。……1年生なりに、“好き嫌いが無い、何でも食べられる子”を見せたかったのでしょう。
(内緒の話ですが、園児たちが帰った後に、こっそり減らしてもらいに来た子が数人いたようです。かわいいですねえ。)
しかし、この1年間で、1年生の子どもたちが見事な成長を遂げたことは確かです。
この子たちならきっと、立派な2年生として、新1年生のよき“お兄さん・お姉さん”になってくれることでしょう。
▼ 2013/03/06(水) 「削り節体験」参観



昨日(5日)、2年生の「削り節体験」が行われました。
そして、その様子を、三島市教育委員会の指導主事や市内のレストランのシェフまで来校し、参観されました。来年度の三島市の<食育>をさらに盛り上げることを念頭に置いた、小学校での教育実践の参観だということです。
本校でも、この「削り節体験」の価値の大きさを感じ、つい最近、「かつお」のどの部位が「かつお節」になっていくのかが一目で分かる模型を購入しました。
子どもたちは、この模型を使っての栄養士の説明に、大きくうなずきながら、各テーブルに置かれた本物の「かつお節」と見比べていました。
2年生は、3年生になったら、<昔の道具>の勉強をします。
この「削り器」も、その一つなのかもしれません。昔から人は、よりよい“食”に対して、このような様々な工夫を施していたことを感じ取った子もいるかもしれません。
生まれて初めての体験に、子どもたちはみんな、楽しそうに、そして夢中で取り組んでいました。
▼ 2013/03/01(金) 5年生&6年生の交流会



6年生と下学年との交流会も、今日の5年生とのもので最後になりました。
5年生は、6年生に「全員リレー」で臨みました。……でも、さすがは6年生。それを受け入れながらも、5年生にハンデを与えました。
① 5年生がスタートしてから3秒経ったら、6年生がスタートする。
② 5年生は、人数合わせで2回走る人を、足が速い人にしても構わない。
このハンデが、勝負を面白くさせてくれました。抜きつ抜かれつの大接戦です。5年生も6年生も、大興奮。リレーを応援する他学年の子どもたちからも、大きな声援が飛びます。……何と、6年生に勝った5年生のチームもありました。
6年生の実行委員のみなさん、どの学年との交流も、全て楽しいものでしたよ。きっと、ここでの触れ合いは、在校生の心に残る思い出の一つになったとことと思います。
▼ 2013/03/01(金) 6年生を贈る会<その5>



各学年や先生方の出し物を受けて、6年生がお礼の出し物で、会を締めくくろうとしています。
歌う前に、6年の代表児童が、各学年に向けて順番に、今日のお礼と来年度に向けてのエールを送りました。
すると、それに応えて、1年生の子どもたち、2年生の子どもたち、3年、4年、5年……と次々に、各学年の子どもたちが声をそろえて、「はいっ!」と返事をしていくではありませんか。6年生の頼もしさに対しての、自然の反応だったのかもしれません。
『あなたにありがとう』の合唱は、体育館の空気を静かに震わせました。感極まって涙を流している6年生、先生方……。
アーチをくぐって退場していく6年生の姿に、(この子たちは、あとわずかで、本当に<卒業>していってしまうのだ。)と改めて実感させられ、胸が熱くなりました。
5年生を中心に企画・準備・運営を行ってきた「6年生を送る会」。
6年生のおかげで、5年生が<最上級生>を意識でき、他の学年の子どもたちも心を一つにできた機会となりました。
みんな、本当にごくろうさん。……そして、6年生は、在校生の気持ちに応えて、残りの日々を大切にしていきましょうね!