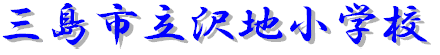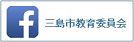つきましては、ブログのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている場合には、大変お手数をおかけいたしますが、変更後の新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いいたします。
今後も、引き続きご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■変更時期
2023年1月30日より
■変更前: 旧ブログ(http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m110/)
■変更後: 新ブログ(https://schit.net/mishima/sawaji-e/)
メッセージ欄
2016年9月の日記
▼ 2016/09/20(火) 社会科の公開授業 2
与えられたグラフに、子どもたちは飛びつきました。4種類のグラフを元に、“謎解き”に挑戦するかのような前向きな姿勢を見せました。
実は、「全国学力・学習状況調査」で、例年子どもたちにつまずきが見られるのが、このグラフや表の読み取りなのです。国語の問題の中で、文章と共にいくつかのグラフや表が与えられ、そこから読み取ったことを文章と関連づけていく力が、全国的に見ても弱いのです。
グループの仲間同士で、頭をすりつけ合うようにしてグラフをのぞき込み、日本における「食生活の変化」と「食料生産への影響」についての関連を、根拠を元に解き明かそうとしています。
子どもたちは、パンの原材料である小麦、また、乳製品、肉類、果物等の自給率が年々減少し、逆にそれらの輸入量が増加していることに気づきました。中には、農業・林業・水産業に携わる人口が減ってきたことや、他や畑の面積の減少等に気づけた子も、ちらほらといたようです。
やはり、グラフの読み取りはなかなか難しいようです。でも、だからこそ、授業者は、このような場を設けることを大切にしているのでしょう。“謎解き”を楽しみながら、子どもたちに力をつけさせようとしているのです。
グループでの発見を、黒板の前に集まったみんなの前で、順番に発表していきます。聴いている子どもたちは、一生懸命メモをとっています。
そして、授業者は、一人ひとりに、この発表を受けてつかんだことを、自分の言葉でまとめさせました。その際に、「自分の言葉でまとめるのが難しい人は、これを持っていって。」……と、今日の授業をまとめるためのヒントカードを用意していました。
それを持っていった子、持っていかなかった子―きっと、どの子も、今日の学習をしっかりまとめられたことと思います。


▼ 2016/09/20(火) 社会科の公開授業 1



2時間目、5年1組での社会科の授業が公開されました。『わたしたちの生活と食料生産』という単元の仕上げの段階で、“これからの食料生産”について考えていく学習内容でした。
授業の最初に電子黒板に映し出されたのは、2種類の「朝食」―<和食>と<洋食>の写真です。授業者はそれを提示して、40年前と現在の「朝食」にどのような違いがあるかを投げ掛けました。
写真に食いついた子どもたちからは、「主食がご飯からパンに替わってきた」ことや「魚より肉を食べることが多くなってきた」こと、「しゃれたデザート(果物)が添えられている」ことや「和食から洋食に移り変わってきた」ことなどが、次々と挙げられます。
そして、それを受けた授業者は、「こうした食生活の変化は、日本の食料生産にどのような影響を与えているか」を、グループで予想を立てさせる場を持ちました。
すると、ほとんどどのグループでも、「洋食に使う食材の、外国からの輸入が増えたのでは……」という予想を立てました。
そこで、授業者が、その予想が本当に正しいかどうか、しっかりした根拠をもとに考えさせようと、各グループに与えたのが、様々なグラフが示された2枚のプリントでした。
「食料品別の輸入量の変化」・「主な食料の品別自給率の推移」・「産業別の人口の割合の変化」・「土地利用の変化」―さあ、子どもたちは、この4つのグラフから、何をつかみ取ることでしょう。
▼ 2016/09/19(月) 参観・懇談会 4



「参観会」が終了後、「懇談会」が開かれました。
6年の保護者は、『薬学講座』を行ったさわやかルームにそのまま残り、今度は、校長先生を講師とした「懇談会」を行いました。
校長先生は、今年度、各クラスで繰り返し実践させることになった<エンカウンター>を、保護者の皆さんに体験してもらう場を設けていました。
どなたもにこやかに周りの保護者と関わり合い、“温かく対等な人間関係づくり”を実感しているようでした。きっと、この<エンカウンター>の価値を理解していただけたことと思います。
体育館では、5年生の保護者を対象とした『家庭教育講座』が行われていました。三島市の家庭教育支援員やアドバイザーを講師としてお招きしての講座です。
……でも、参加された保護者が少なかったので、互いに心を開いて話し合うような雰囲気作りは難しそうでした。
しかし、講師の方々は、最初に、<アイスブレイク>という、“人と人のわだかまりを解いたり、話し合うきっかけをつくったりする”ためのちょっとしたゲームを行いながら、参加者の心を柔らかくほぐしていきました。
そして、3人ずつのグループを作らせ、『子どものほめ方・叱り方』についての話し合いの場を設けることで、一人ひとりが自分を見つめ直す声を引き出していきました。―参加された方々は、きっと、「我が子のやる気の引き出し方」のヒントをつかめたことと思います。
講師の皆様方には、家庭教育に対する価値あるご提言をいただき、心より感謝申し上げます。
▼ 2016/09/16(金) 参観・懇談会 3
1階のさわやかルームでは、6年生が「薬学講座」を開いていました。
学校医さんや三島警察署の少年サポートセンターの署員さんが、講師として来校されました。
部屋を覗くと、ちょうど、保護者の皆さんの手から手へ、シャーレに入った“レバー”が手渡されていくところでした。
この講座では、<薬の正しい使い方と、お酒・たばこ・薬物の害を知る>ことを目的としています。
この“レバー”は、アルコールをかけることによって変化が生じる様子を見せてくれていたのです。“肝臓”が、お酒によってこんなに傷めつけられるのを目の当たりにした子どもたちと保護者の皆さんからは、しばらくの間、どよめきが起こっていました。
他にも、「薬」も飲み方によっては、病気を治す効果もなく、逆に悪影響さえ及ぼすということや、「たばこ」が及ぼす自他の健康への大きな害、そして、「薬物」と呼ばれているものが、<人間から人間らしさを奪っていく>恐ろしさが、熱く語られていきました。
スクリーンに映し出される様々な画像に、子どもたちは驚きの表情で、食い入るように見入っていました。中学への進学を半年後に控えた6年生たち―<自分の人生は、自分の命は、自分の強い意志で守っていこう>という気持ちを抱いてくれれば幸いです。
価値ある学習の場を与えてくださった講師の皆さん、ありがとうございました。


▼ 2016/09/16(金) 参観・懇談会 2
4階のさわじルームでは、4年生が「健康教室」を開いていました。
東部健康福祉センターの健康増進課、三島市健康づくり課、子育て遊び研究協会、三島市健康づくり団体……この教室を開くために、いろんな方々が、講師として来校してくださいました。
この学習は、「こどもから大人へのメッセージ事業」として、<たばこが身体に及ぼす害>について学び、親御さんたちに、大人たちに、<禁煙>を促そうという意図がありました。
講師の方々は、可愛らしい様々な動物のかぶり物を着け、劇を行いながら学習を展開させていきました。「ライオン王様」の健康を気遣った「りす」「熊」「うさぎ」が、「パンダ先生」の指導を元に、たばこを吸わないように勧めようとしていくストーリーは、子どもたちに分かりやすく、染み込みやすいものでした。
子どもたちが楽しそうに見入っている姿を後ろから見守る保護者の皆さんも、きっと、“4年生”という、この時期の発達段階から指導していくことの価値を感じとられたことでしょう。
楽しく価値ある学習の場を与えてくださった講師の皆さんに、心より御礼申し上げます。