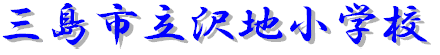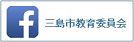つきましては、ブログのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている場合には、大変お手数をおかけいたしますが、変更後の新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いいたします。
今後も、引き続きご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■変更時期
2023年1月30日より
■変更前: 旧ブログ(http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m110/)
■変更後: 新ブログ(https://schit.net/mishima/sawaji-e/)
▼ 2015/11/01(日) 土曜参観会 5



この「土曜参観会」は、“土曜日”での実施、そして、“3時間目から5時間目までの公開”ということで、
「お仕事が休みの方が多い」こと、
「都合のつく時間帯に来ることができる」こと、
「兄弟姉妹がいる家庭はどのクラスにもゆっくり顔を出せる」こと、
「他のクラスや他学年の授業の様子も参観できる」こと、
「授業時間以外の学校生活の様子も見られる」こと
……等々、様々な利点を考えて設けられています。
上の写真は、「給食」の様子を参観している親御さんたちの様子です。
「わあ、すごい。昔と違うねえ。」
「ああ、最初に、もっと食べたいものをおかわりしちゃうんだ。」
「いい匂い。おいしそうなメニューだなあ。」
と、興味深げに教室を覗いている親御さんがたくさんいました。
また、お弁当を持参され、<食事処>として開放された部屋で食べていらっしゃる方も、10人近く見られました。
こうした熱心な方々の姿を目にすると、この「土曜参観会」の価値を実感します。多くの皆さんのご来校に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
<*しかし、親子が一緒に活動しなければならない>場が設けられると、“自由参観”では無くなってしまいますね。今後の反省点として、検討していきたいと思います。>
▼ 2015/11/01(日) 土曜参観会 4
同じく5時間目、体育館では3年生が『健口教室』(口の健康)を開いていました。
6月の上旬に、3年生の子どもたちは、すでに一度この教室を体験しています。しかし、親御さんにも共通理解していただくことで、その効果がいっそう高まることをねらいました。(「学校保健委員会」の事業の一つにもなっているのです。)
土曜日にもかかわらず、歯科衛生士さんが、講師として来校してくださいました。
まずは、スクリーンに映し出された画像をもとに、本校児童の<虫歯>に関する実態が述べられ、そして、<虫歯>ができる原因について、食品・食べ方(噛み方)・生活習慣等の様々な視点から解説がなされました。……子どもたちはすでに学習していることですが、やはり、親御さんも共に理解することで、家庭での支援の仕方が変わってくるはずだと感じさせられました。
そして、<歯の正しい磨き方>について学ぶ時間が始まりました。
子どもたちは各自、昼休みに、「カラーテスター(歯垢染色剤)」で、歯を赤く染め上げてきています。
その色を上手に落とす<磨き方>を親御さんにも知っていただく場が設けられたのです。歯科衛生士の丁寧なご指導のもと、先に、子どもたちに自分で磨かせ、続いて親御さんに“仕上げ磨き”をしてもらいます。(小学3年ぐらいまでは、親御さんによる“仕上げ磨き”が必要なのだということが話されました。)
多くの親御さんは、きっと久しぶりに、我が子の歯を磨いてあげたのではないでしょうか。子どもたちもきっと、久しぶりに、親御さんに歯を磨いてもらったことと思います。見ていて何か、ほんわかと微笑ましい空気を感じました。子どもたちが、うれしそうな表情で、親御さんになすがままにされている姿は、本当に幸せそうでした。
低学年の保護者の皆さん、お子さんの「口の健康」を守るために、さらに、親子の心をつなぐためにも、“仕上げ磨き”をしてあげてはいかがでしょうか?


▼ 2015/11/01(日) 土曜参観会 3



5時間目、6年生は「修学旅行説明会」を開きました。
「修学旅行」は、他の行事と違って、多額な費用がかかりますし、事前の準備も親御さんの大きなご支援を必要とします。「修学旅行」というものを親子で共通理解して欲しいという担任たちの思いが、この会にはあったのです。
初めに、「修学旅行実行委員」たちが紹介され、一人ひとり順番に抱負を述べていきます。どの子もはきはきとした口調で、熱い思いを吐き出していました。これだけで、保護者の皆さんには、子どもたちの「修学旅行」に向けられた意欲が伝わったかもしれません。
続いて、<「修学旅行」の誓い>を、子どもたち全員で声をそろえて唱えます。
「意見を伝え合い、支え・助け合い、チームワークを深められる、修学旅行にしよう!」―教室に力強い声が響き渡りました。もうこれで、子どもたちの心の底からの叫びが、保護者の皆さんの心の奥にもすっかりしみ込んでいったことでしょう。
そして、「修学旅行」についての細かな説明の時間に入りました。子どもたちは「しおり」を、親御さんは「プリント」を食い入るように見つめながら、説明に耳を傾けていました。
子どもたちはきっと、親御さんと心を一つにして、親御さんへの感謝の気持ちを抱きながら、12日の出発に向けた準備に取りかかることでしょう。
6年生の保護者の皆さん、子どもたちの大きな思い出作りを、温かく支えてあげてくださいね。ご協力、よろしくお願いいたします。
▼ 2015/11/01(日) 土曜参観会 2
4時間目、4年生は保健体育の学習として『誕生学』を実施する時間を設けました。これは、「あざれあ地域協働事業」 に申請して採択されたもので、土曜日にもかかわらず、『誕生学』専門の講師が来校してくださいました。
お話が始まる前に、子どもたち一人ひとりに、ハート型に切り抜いた色紙が1枚ずつ配られていました。実はそこに、“0.1㎜”の穴が空けられていたのです。
そして、この“0.1㎜”は、「人間誕生」のスタートの大きさだというお話から始められました。子どもたちからは、当然ながら、「ええ~っ!」という驚きの声が上がりました。
それが、お母さんのお腹の中で、少しずつ少しずつ大きく育っていく様子が、分かりやすい大型絵本で紹介されていきます。手も、最初の頃は、指が全部くっついていた……そんなお話にも、子どもたちはまたまた目を丸くさせています。―いつしか、「人間誕生」の“神秘”に引きずり込まれているようでした。
次に、赤ちゃんが「誕生」する時の“神秘”が、人形と骨盤の模型を使って話されました。楕円形をした頭の赤ちゃんは、お母さんの体の中から、あごを引いて、さらに骨盤の形に合わせて回転しながら出てくる……そんなお話にはもう、子どもたちは、信じられないという表情をしていました。
最後に、赤ちゃんが誕生する前、誕生した時、誕生した後の一瞬一瞬の感動をまとめた映像が流されました。……家族の大きな喜びが、たくさんの笑顔やうれし涙で表現されています。子どもたちの目は、画面に吸い込まれていきそうでした。後ろで見ている親御さんの中には、目を潤ませている方も見られました。
神聖なひとときでした。感動的な時間でした。子どもたちはきっと、自分がいかに大きな喜びに包まれて誕生し、たくさんの愛情のもとで育てられたのかを改めて実感できたのではないでしょうか。……これからの生き方にも影響を与えてくれるような、価値ある学習だったと思います。


▼ 2015/11/01(日) 土曜参観会 1



31日(土)、「土曜参観会」が開かれました。3時間目から5時間目までの都合のつく時間に自由に来校していただく“自由参観”です。そして、せっかく親御さんがいらっしゃるのだから……と、いくつかの学年は“特別授業”を組みました。
2年生は、3時間目に「北上えこくらぶ」の方々を講師にお招きし、『どんぐりを学ぼう』という生活科の授業を行いました。
最初に、運動場南西側の“沢地森”に、子どもたちも親御さんも一緒に、<どんぐり>を拾いに行きました。ただし、“一人一個”という条件に挙げられました。
全員が拾い終わったのを見計らって、運動場に戻ると、「えこくらぶ」の4人の方々が、それぞれ異なる葉っぱが付いた木の枝を持って待っていました。―自分が拾った<どんぐり>がなっていた木の葉っぱの所に集まろうという訳です。
子どもたちは4種類の葉っぱをじいっと見比べながら、あっちへ行ったりこっちに来たり……。葉っぱの違いを見分けるのは、なかなか難しいものです。
その後、正解が発表され、その4種類の葉っぱの木になる<どんぐり>についての解説がなされました。“沢地森”で拾ったのは、その中の2種類「マテバシイ」と「スダジイ」で、残りの2種類は、「クヌギ」と「クリ」の葉っぱでした。
同じ<ドングリ>の葉っぱでも、周りが円かったり、ぎざぎざしていたり、裏の色が違ったり……。子どもたちは、今まで意識しなかったことについての新たな発見に驚いているようでした。また、子どもたちに<どんぐり>への愛着を抱くようにと、「どんぐり笛」や「どんぐりごま」、だんぐりで作った「やじろべえ」も紹介してくださいました。
自然に恵まれている沢地地区―子どもたちに、自然を大切にしながら、自然によって心を育んでいくための、よい機会になったことと思います。